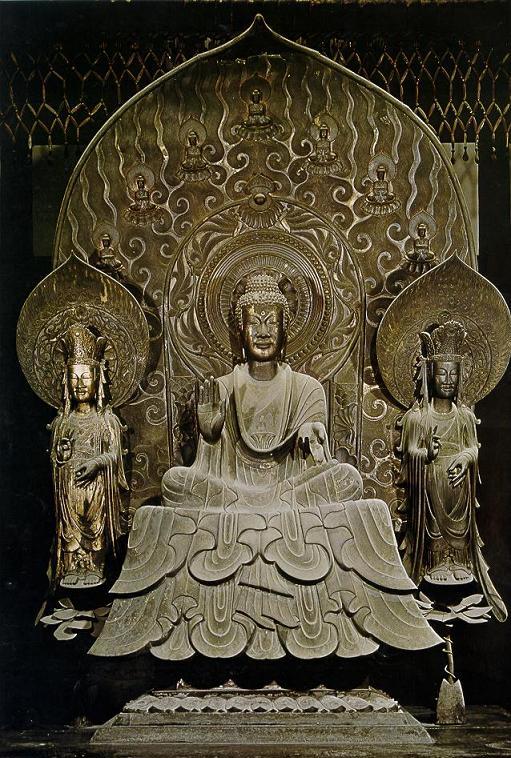以下は「理科系のための哲学」のために書いた文だが、ここにまずは置いておくことにする。
--------------
このサイトは理科系のための哲学とうたっているのだが、そもそもいったい哲学とはなんなのか、と端的に聞きたいかもしれず、そう言われても、そうそう簡単に答えられないのが普通だ。しかも、特に理科系の僕らが哲学を勉強していったいなにかいいことがあるのか、と反応するのも普通のことだ。実際、役に立たないことをわざわざするほど暇でないのは分かっている。しかし、ここを読んでいる時点ですでに片足を突っ込んでいるわけで、少しお付き合いして頂こう。
まず、哲学という言葉だが、これは何のことを言うのか。サイトの趣旨のところにも書いたが、日本語の「哲学」はいろいろな使われ方をするので、幅が広い。学問としての哲学の反対方向の最たるものは、人生哲学とか経営哲学とか、あの人は哲学がある、とかいう使われ方であろう。そういうときの哲学は、ほぼだいたい「信念」とかそういうものを指すわけで、たいていの日本人には語感があるだろう。というか、実際のところ哲学をそういう意味だと思っている人も多いかもしれない。最初にはっきりさせるが、ここで話そうとしている哲学は、そういういわば俗な意味の哲学のことではなく、正統派の哲学である。
では、ここでの哲学とはなにかというと
「世の中のなんでもいいので「なにか」の本質はいったいなんなのかということを論理的に追及すること」
である。ここで重要なのは「本質」と「論理的」である。
まず本質だが、この言葉もそこそこ手垢にまみれていて、日常でもふつうに使われる言葉だ。なにか事があったとき、その原因の元の元を追及して、事の起こる原因をもっともきれいにエレガントに説明できる原因であるところのものを抉り出して見せると、本質を突いた議論、などといって褒められる。では哲学の本質はこれと違うか、というとそれは同じである。しかし、哲学では常識を遥かに超えて本質を問い続けるところが違う。
たとえば、「見えるとは何か」という問いがあったとして、その本質をどう答えるだろうか。たぶん、理科系の我々であれば「空間に物体と光源があって、その物体からの反射光が眼球に入り、網膜に像を結び、これを視神経で脳に送り、脳にできあがった何らかの神経回路によってそれが解釈され、見える」などという答え方が返ってくるであろう。ここまでであれば何ら哲学ではなく、これはほぼ科学の話である。光学や神経科学、脳科学などの科学領域で説明した「見える」の本質である。現代人ならば大半の人はこれで納得するはずだ。
では、哲学ではどうなるか、というと、ここでの説明をもう一段階どころか、ほぼ際限なく問い続けるのである。例えばこの例なら、「見える」が最終的に脳で作られるとすると、物体も光源もなくとも見えるはあるはずだろうが(現代ならさしずめ脳に電極を挿入するであろう)それは見えると呼べるのか否か。あるいは、人間が見えると言っている対象は、網膜の像のことなのか、あるいは視神経の生理学的変化のことなのか、あるいは物体と光源のことなのか、いったいどれを見えると称しているのか、とか。あるいは、AさんとBさんの「見える」は本当に同じ事態と言えるのか。それを証明する手段はあるのかないのか。もし、なければそもそも見えるという事態を一般化できないことになるではないか。
などなどきりがないのだが、ほとんど、揚げ足に近いほど、嫌がらせと言ってよいほど、病気じゃないだろうかと言いたくなるほど、執拗に食い下がって、その「コト」の本質を見極めようとする努力をすることが、哲学の定義で言うところの「本質」なのである。問い掛けを途中で止めてはいけないのである。
もう一つの特徴は「論理的」であるが、これは理系の人ならとっても親しいのですぐ分かるであろう。上述の本質の問い続けにおいても、とにかく論理で問い続け、それに論理で答えないといけない。途中でめんどくさくなって「物事ってのはそういうものだ!」とかいって論理的追及を中断してはいけないのである。ちなみに一般社会では、ふつうこれである。特にさきほどの人生哲学とか経営哲学になると、そういうことを主張する人を相手にしつこく追及したりしていると、あるところで「信念」や「常識」とかいう化け物みたいなのが出てきて、ガツンと中断され、「そんなことを言うならお前は社会で仕事をする意味も資格もない!」とか「誰のために生かしてもらってると思ってるんだ!」とか叱られて終わってしまったりするのがオチである。その手の哲学を俗だと言ったのはそういうわけである。
哲学は役に立たない
ここではっきりするのが、哲学は役に立たない、というよくある有名な命題の正しさであろう。そう、役に立たないのである。というのは、本質の追求というのは、適当なところで止めて提供するからこそ世の中の役に立つのであって、それを止めずに問い続けても現実から遊離するだけで何の得にもならないのである。先の「見える」の例だと、物体→眼球→脳→見える、というところで止めることで、これをコンピュータや機械に置き換えていろいろなサービスを生み出したりして、ひいてはお金になったりするわけである。
それ以上に「見える」というのを追及してしまったら果てしなく問いは続き、どこかで本質に達したとしても、だいたいが現実離れした着陸点となったりする。たとえば、この例であれば、哲学的に「見えるという具体的現象があるわけではない。これはめいめいの人間の主観が社会で合意した挙句に現れる観念なのであり、眼球が物体を見ているというのは単なる物理的一解釈に過ぎず本質ではない」とか言ったとして、はて、いったいこのステートメントをどうやって世の中に役立たせればいいか、皆目分からない、ということになってしまうのが普通だ。
数学は哲学か
理科系の人であれば、論理的といえばまず数学を思い浮かべるであろう。前述は「見える」ということを追及した例だったが(哲学的には認識論という)、数学はどうだろう。数学は完璧な論理のもとに構築されており、正しいことしか現れない。あいまいなものはすべて論理的に却下されるので、数学の論理を追っているときに「これが物事ってもんだ!」という思考停止は入らないかに思える。では数学は哲学なのか?
答えはNOである。まず、哲学は神羅万象すべてを対象とするが、数学はそうではないという前提の違いがあるが、それはまずは置いておこう。数学の論理展開のもとには公理というものがあるが、いわばそれが中断に相当するのである。公理とは「同じ長さの線分は重ね合わせられる」とか「平行線はどこまで行っても交わらない」とか思いつくが、そういうものである。人間の常識として当たり前で直観的で誤りようのないものを公理とするわけだが、哲学はそれをも疑い、その本質の追求へ持って行こうとする。あと、数学は「何かを何かとおく」という人為的な約束事を作って、それを元に論理を発展させ、さまざまな数学分野を広げて行くが、その行為そのものも哲学の追及の対象になる。
数学側とすれば公理や約束事は数学の礎石であり、それが人為的であろうと、作為的であろうと、それを元に数学が発展すればそれでよし、とする。当たり前である。ルートマイナス1はあり得ない。その通りだ。でもルートマイナス1をいったん認めてそれにiという名前を付けて追及してみよう、と、あるときだれかが考えて、そのおかげで数学は複素数論という膨大な体系を作り出した。しかも、これはえらく役に立つ代物で、あのとき頑なにルートマイナス1を拒否していたら、世界はえらく狭くなったであろう。あと、先の例の、平行線が交わらない、も交わることにすればリーマン幾何学が構築されることもよく知られている。
哲学はルートマイナス1を否定しないが、その意味を問おうとするであろう。ここで、数理哲学という分野があり、これは、そういった数学における論理の本質を哲学的に問う学問である。思い出すが、むかし、とある大学のある著名な数学者とセミナーをやったことがあり、その先生は代数学の大家なのだが、数理哲学の研究者たちのことを「あいつら、まったくに下らない、役に立たないことばかりしやがって」とこき下ろしていた。しかしながら、先生の代数学が世間の役に立つかというと、ほとんど役に立たない。その役に立たない紙の上の数学をする先生に、さらに役に立たないと言われているのが哲学なのである。いかに哲学が役に立たないか思い知らされる話だ。
もっともちなみに代数学は、暗号理論と符号理論に期せずして役に立ってしまい、当の代数学者もびっくりしたそうだ。暗号とデジタル符号化なしに今のネット社会はあり得ないので、代数学はこれひとつで元を取ったと言ってよいほど世の中の役に立ってしまったのである。しかし、依然として代数学の中の大半の定理は役に立たないのは変わらない。将来どっかでまた役に立つかもしれないが。
パラダイムの変革
そう考えると哲学も、今は役に立たないだけで、将来はどこかで役に立つことがあるのであろうか。これについては、あるいはそういうこともあるかもしれないが、ほとんど望みが薄い。先も言った通り、数学や、ましてや物理学などの科学がなんで世の中の役に立つかというと、世の中にある前提を「与えられたもの」として礎石に置くからである。その礎石が世の中で皆に認知されているものであれば、その上に築いたものはどこかで世の中の役に立つのである。
しかし、哲学はその「今の世の中で前提となるもの」自体を疑ってしまい、その本質を見極めようとしてしまうので、それは役に立たないのが普通なのである。しかし、当然ながら、もし、その「今の世の中」から時代が百年とか二百年とか進んで、その「前提」があるとき何らかの影響で変わったとすると、そのときにはあるいは劇的に役に立つものになる可能性はある。いや、哲学の命題など直接に役には立たないが、その「前提が劇的に変わる」という社会現象に非常に大きな影響力を持つのが哲学であり、そういうことを目指すのが哲学の仕事と言ってもいい。
すなわち、現在の人間が「当たり前の前提」と思っていることを、覆すのが哲学で、それを変更させようと骨折るのが哲学の道なのである。この、時代に共有された当たり前の前提をパラダイムというが、そのパラダイムを疑って、新しいこれまでにないパラダイムを作り出そうという努力が哲学にはある。しかしその新しいパラダイムが、今のパラダイムにとって代わるには、通常非常に長い時間がかかる。
僕らだって、アナログ社会からデジタル社会、そしてインターネット社会へのシフトを現に経験した。これは我々のパラダイムを確実に変えたはずだ。たとえば、むかし僕らはレコード盤というビニールの板を物理的に所有していないと音楽を聞けなかったが、今じゃそんなものは無くなり、モノリスみたいな黒い板にイヤフォンを差し込めば音楽が無尽蔵に聞ける。恐ろしいことである。ほとんど魔術並みである。これは僕らにとっての音楽作品というものの意味をだいぶ変えてしまった。
さて、デジタルとインターネットの話になったが、これは哲学のおかげでこのようなパラダイムの変革が起きたのだろうか。そんなはずはないだろう、と言うであろう。どこの哲学者がデジタルとネットワークの概念を提出したか。してないじゃないか。デジタルはその昔、電気工学者のナイキストと数学者のシャノンが理論的基礎を与えてコンピュータの出現で今の姿になったはず。哲学なんかなくったって、パラダイムシフトは起こるし、むしろ哲学なんか結局は、どうでもいいことを根掘り葉掘り詮索しているだけで、パラダイムの変革の役にも立たないんじゃないか。パラダイムシフトは現実社会の具体的変革を核にして起こるのだ。と言うかもしれない。
おそらく言っていることは表面上は、正しい。だが、もし、そうであれば、私はこの「理科系のための哲学」などという企てをするわけがない。これは自分の一種の仮説になるが、このパラダイムの変革の立役者になった人々のウラには哲学が隠れているはずだと思うのだ。具体的な哲学の学説は無いかもしれない。しかし、哲学的直観がその立役者たちのウラにあるはずだ、と私は見ているのである。特にデジタルとインターネットの物理的なインフラが出来上がって世界に浸透して、2000年になり、15年ほどの間に次々と起こったデジタル情報社会の本質的なパラダイムシフトの裏には哲学が大いに与ったのではないか、というのが私の仮説なのである。
改めて哲学とは何か
少し話を戻そう。哲学とは何かという話だった。まとめると、物事の本質を論理的に問い続けること、である。こうして書くと当たり前に見えるのも面白い。実質を求める社会人にこの文句だけを言えば「それこそ我々に必要なことじゃないですか!」などと実質的反応をするかもしれない。なので付け加えると、哲学では、今現在の社会の規範に沿って生きて仕事して生活する人から見ると「常軌を逸して」本質を論理的に問い続けること、という但し書きがつく。
さて、以上がこのサイトで言うところの哲学の定義なのであるが、このようなものが最初からあったわけではない。哲学が産まれたとされるのは通常、ギリシャで、紀元前の話である。歴史の話をし始めると長くなるので、ここでは極力端折ることにするが、乱暴に言うと、かの有名なソクラテスが、現代の哲学の原型を作った人と言えるだろう。しかしソクラテスを読んでみると分かるのだが、さきほど与えた哲学の「本質」と「論理的」の二つを満たしていない。ソクラテスの、論理を縦横に使って結論を導くさまは感動的である。しかし、本質の方はまだ、与えられたものとして、一種の信念、信仰として前提されていることも分かるだろう。
その後、プラトンがソクラテスの弟子として現れ、そしてアリストテレスが今度は科学の原型を作った哲学者として現れている。しかしながら、これらギリシャの三羽烏もその時代のパラダイムの枠の中で思考した人々と、言えるだろう。ただ、どうしても付け加えておきたいが、この三人のした仕事のすばらしい「高貴さ」は現代人には及び難いものがある。人類がまだ高貴であることができた幸せな、ノイズのない、黎明期だったのであろう。
デカルトの意味
というわけで、ギリシャの哲学は、まだここで説明した意味での哲学ではない。では、前述した意味での哲学はいつ生まれたのかというと、それは、デカルトからである。このサイトのトップページはデカルトの肖像画から始まっているが、それは、そのせいである。デカルトが何をしたかというと、物事の「本質」を問い続け、それが壁にぶつかってついに止まってしまうまで問い続けたのである。デカルトは、これを明快な形で行った世界で最初の人だったのである。最後にぶつかった壁に彼は「我思うゆえに我あり」という言葉が書かれているのを、見たのである。
歴史的に言っても、デカルトは近代哲学の始祖である。彼によって「物事の本質を論理的に常軌を逸して問い続ける」ということが初めてなされたわけだ。次の章では、そのデカルトのやった仕事を紹介するので、そこでまたくだくだ書くが、ここで予告をしておこう。結論から先に言うと、デカルトは科学に基づく「工学」を初めて明快に始めた人だったのだ。
思い出して欲しい。デカルトの時代は、かのガリレオが地動説を提出したせいで宗教裁判にかけられ有罪となった時代なのだ。ほぼあらゆる重要なことは神によってトップダウンで決められる時代だったのだ。その時代にデカルトは、神のトップダウンはそのままにしたまま、「人間だけで決められる領域」というものがあるということを初めて明快に言ったのである。そこでは人間が人間の主人だ。そして科学をベースにした工学によってその「人間だけの領域」を無限に広げて行くことができる、ということを宣言したのである。実は、これが「我思うゆえに我あり」のとても大切な意味だったのである。
こうして、僕ら現代のテクノロジー社会に生きる者はみな、デカルトの恩恵を受けているのである。そして、ということは、僕らは知らずして「デカルトに規定されている」のである。このパラダイムはいつ変革するのであろうか。いや、変革は既に起こっているのではないだろうか。それはデカルトの興した哲学によるパラダイムの変革として現れるはずではないだろうか。そして、それを語るのが、このサイトの主旨である。